
2021.01.29
シリーズ・徒然読書録~浅田次郎著『大名倒産 上・下』
あれもこれも担当の千葉です。
読書は好きで、常時本を持ち歩く癖が付いてしまいましたが、読み方は極めて大雑把、何かしら記憶のどこか、心の片隅にでも蓄積されていれば良いという思いで雑然と読み流しています。暫くするとその内容どころか読んだことさえ忘れてしまうことも。その意味で、読者の皆様には退屈でご迷惑かとも恐縮しつつ、ブログに読書録なるものを記してみるのは自分にとって有益かも知れないと思い、始めてみました。皆様のご寛恕を請うところです。
徒然なるままに読み散らす本の中から今回取り上げるのは、浅田次郎著『大名倒産』(文藝春秋刊)。『流人道中記』同様、昨年に読んだ浅田作品。一年ほど前でしたが、新聞広告を見て図書館で借り受けました。

隠居の父・前藩主が企む前代未聞の藩の計画倒産。縁の薄い末息子に腹を切らせてのお家幕引きが謀られます。お家を倒産・滅却せんとするご隠居様一党と、再興せんとするお殿様一党との間に繰り広げられるあれやこれや。終いには謙信公の隠し金山が積年の窮状を解決するというどんでん返しのドタバタ時代劇。
大名の計画倒産という大きな書割は巧妙ですが、深みに欠けた冗長な展開で、この後の作品である『流人道中記』などと比べると、浅田作品の中では気合不足のやっつけ作品という印象を持ちましたが、二百有余年続いた太平の世がもたらした硬直化した社会の矛盾を浮き彫りにした視点や、落語のような軽妙洒脱な文章と、大団円の高揚はさすが浅田氏、お見事です。
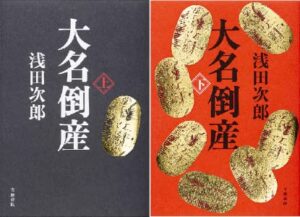
印象に残った巧みな文章を幾つか列記してみます。
『夏陽の翳りかけた庭に、嗤う(あざわらう)がごとく蜩(ひぐらし)が鳴き始めた。』
『池泉に闇が下りてきた。庭先で平八郎の焚く蚊遣りの煙が、芳しく(かぐわしく)流れこんだ。』
『お庭に面した客間に腰を下ろしたとたん、すうっと汗が引いたのは、楠の葉裏に漉された風が、松ヶ枝を渡り百日紅を巻き、池の面と苔を撫でて、桔梗や槿の侘びた香りをそっくりそのまま座敷に招き入れていたからであった。座敷から眺めるのではなく、庭のただなかの亭(ちん)に座っているような気がした。・・・こうして廊下を歩んでいても、時折ふと足が止まってしまうのである。お庭は歩みに合わせて徐(おもむろ)に相を変えてゆき、その移ろいはみなことごとく美しいのだが、ある一瞬に思わず立ち止まってしまうほどの、全き景観が出現する。一枝の過分もなく、一草の不足もないと思える完璧な風景であった。・・・池泉の向こう岸に滝が落ちている。荒くもなく、細くもなく、銀色の反物を滑らせたような滝である。その先は緑なす丘になっているが、頂きに繁る杉木立は滝の上だけ截然(せつぜん)と払われていた。その空隙に、隣屋敷の楠の巨木がぴたりと嵌っている。これは風景ではなく、兄の描いた絵だと思うた。隣屋敷の濃密な楠を借景として、やや淡い杉の線を描き、その手前に薄緑の笹を敷き、さらに明るい青苔の付いた岩の間から、銀色の滝が落つるのである。しかもその緑の階調には、少しも企まれた様子がなく、たとえば風の道が標すままに長い時をかけて、その景色が出来上がったようにしか見えぬのだった。』
『誰が見ようと等しく感動する天然の景観を、兄は造り上げたのだと思う。風流をなすは人の才であろうが、天然を造り給うは神の業である。しかしーー。洟水をすする音に興をそがれてふと見れば、そこに佇んでいるのはまさか神さまではなくて、乾坤一擲の馬鹿であった。』
『語らううちに光の帯が天に巻き上げられ、からっぽの宝蔵の中は蜩の声に満ちた。』
『そもそも人情なるものは貧乏より生ずるのであって、さんざ飲み食いして世間を知れば、人は非情になるはずではないか。』
『苦しむでも喘ぐでもなく、やがて和泉守の腕の中で命が脱けた。』
『そう、女の恋は流れ去り、男の恋は積み重なるのである。』
最後に、兄弟も家臣も幼馴染も無類の豪農も、七福神や貧乏神までもが力になりたいと思う、若き無辜の殿様の魅力を端的に表す表現がありました。
『ご決心は変わりませぬか』『決心というものに変わりようのあるはずはない』
『どうしてこの人は、おのれを矜ろう(ほころう)としないのだろう。あらゆる理不尽をすべて呑み下し、押し付けられた苦をことごとくおのが苦に変えることなど、なぜできるのだろう。』


